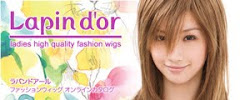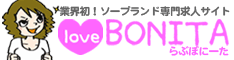木管の柔らかさがシューベルトの「Symphony No 9」での聴き所。豪放としつこいリズムの連続に挟まれて、まさに「天国的」とシューマンが評価した気持ちが分かります。今年はサー・エイドリアン・ボールトのアニヴァーサリー。珍しいところではフィルハーモニアを振ったマーラーでクリスタ・ルートヴィヒが歌っている録音(Christa Ludwig Singt Mahler)が、クレンペラー、ヴァンデルノートが指揮した管弦楽付き歌曲集として組み合わされているCDが面白い。エードリアン・ボールトと言えば"惑星"を3度録音。カラヤンより多い録音回数記録保持者。わたしが英国作曲家に関心を持つようになって聴く回数が増えた指揮者です。それも英国プレス盤を聴くようになって増えました。アナログ盤のコンディションは良いものが多くて、価格もお手頃の価格が多くてオリジナル盤の入門にも最適。この「Symphony No 9」はモノクロ切手ラベルですので、良盤で安定した音質を楽しめます。http://ow.ly/41GmS
このレコードはSOLDOUTになりました。詳しくはこちらをご覧下さい amadeusclassics.otemo-yan.net